| ・ |
病理のDrの話も聞けてよかったです。検診施設と病院とのレベルが同じになるように今後研究会で意見していけたらいいなと思ってます。 |
| ・ |
いろんな施設の画像を見ることが出来、とても面白かったし勉強になりました。乳腺症を考える際どこまでを精査とするのかというラインが難しいなと思いました。 |
| ・ |
しばらく検査からはなれていたのですが、多くのスライド、症例などで検査の進め方、考え方、読み方、レポートの書き方など感覚が戻ってきました。ありがとうございました。 |
| ・ |
今回のように症例を多数見れる機会があるのはとても良かったです。他施設の悩みも伝わってきて共感を持ちながら聞けました。病理との対比があるともっとうれしいです。 |
| ・ |
色々な症例がみられて勉強になりました。日頃悩んでいることはびまん性のlow echoを腫瘤ととるべきか単なる乳腺自体の性状の変化ととるべきかというところでしたので、今回の症例はとても役立ちます。ただ、ポイントを殴り書きしていて後から読むと何のことだったか症例と書いたことが結びつかない事も多いので、この症例の何を話したかというようなアドバイスまたはサマリーというか議事録のようなものがあればいいなと思いました。 |
| ・ |
各施設の今まで見逃した症例や反省症例など見てみたい。勉強になりました。ありがとうございました。 |
| ・ |
機器設定について更に勉強したいと思いました。 |


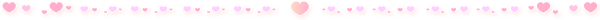
 このたびの東北地方太平洋沖地震において被災されました方々またその関係者の方に対し、心からお見舞いを申し上げます。この時期多くの学会や研究会が中止や自粛など内容の変更を余儀なくされている中、当会はその内容を検討した結果、開催に問題ないものと判断に至り、予定通り開催されました。当日は、ようやく春らしい天気に恵まれ、多くの皆様にお集まりいただきました。また、今回は初めて、事前に症例を募集せず当日持ち寄った症例を検討するという試みを行いました。どれだけの症例が集まるのか全く予測もつかないまま当日を迎えるのは多少不安でしたが、そんな気持ちを吹き飛ばすほど多くの症例が集まり、休憩時間にも席を立つ方が少ない程白熱した会となりました。
このたびの東北地方太平洋沖地震において被災されました方々またその関係者の方に対し、心からお見舞いを申し上げます。この時期多くの学会や研究会が中止や自粛など内容の変更を余儀なくされている中、当会はその内容を検討した結果、開催に問題ないものと判断に至り、予定通り開催されました。当日は、ようやく春らしい天気に恵まれ、多くの皆様にお集まりいただきました。また、今回は初めて、事前に症例を募集せず当日持ち寄った症例を検討するという試みを行いました。どれだけの症例が集まるのか全く予測もつかないまま当日を迎えるのは多少不安でしたが、そんな気持ちを吹き飛ばすほど多くの症例が集まり、休憩時間にも席を立つ方が少ない程白熱した会となりました。  まずは勤医協札幌病院の高橋氏に症例を提示して頂きました。症例は3症例で、まず乳頭直下にある病変で腫瘤と読むべきか、否か判断に迷う症例が提示されどの様に読むべきかを会場の皆さんと共に考えました。
まずは勤医協札幌病院の高橋氏に症例を提示して頂きました。症例は3症例で、まず乳頭直下にある病変で腫瘤と読むべきか、否か判断に迷う症例が提示されどの様に読むべきかを会場の皆さんと共に考えました。  二人目は旭川赤十字病院の長尾氏が用意した症例で、1症例目はマンモグラフィでは指摘する場所はないが、USでは乳管内病変が考えられ、細胞診を施行したところ線維腺腫との判定であった症例を提示して頂きました。画像的に線維腺腫が考えられず、どう解釈すればよいかということでしたが、会場にいらっしゃった病理医の市原先生から病理の立場から細胞診診断はごく一部の細胞で判断を行うことよりこの場合、臨床情報、特に画像所見が細胞診の依頼書に記載されていれば臨床上の問題点に沿った解答を示すことが出来るであろうとのコメントを頂きました。
二人目は旭川赤十字病院の長尾氏が用意した症例で、1症例目はマンモグラフィでは指摘する場所はないが、USでは乳管内病変が考えられ、細胞診を施行したところ線維腺腫との判定であった症例を提示して頂きました。画像的に線維腺腫が考えられず、どう解釈すればよいかということでしたが、会場にいらっしゃった病理医の市原先生から病理の立場から細胞診診断はごく一部の細胞で判断を行うことよりこの場合、臨床情報、特に画像所見が細胞診の依頼書に記載されていれば臨床上の問題点に沿った解答を示すことが出来るであろうとのコメントを頂きました。  一つ目は、サイズが5mm前後の腫瘤に対しての扱い方で、経過観察にはなるものの所見に対して施設からは診断名を記載せねばならず、この場合診断医によってバラバラになってしまうという検診施設での問題についてその取り扱いについてディスカッションしていきました。この様な病変の場合、様々な考え方が出され一つにまとめることは難しかったのですが、会場にいた多くの方達に共通していたのは、今回提示された小腫瘤は全て悪性を考えにくいと判定されたことでした。これは検診を行う上では非常に重要であり、5mm以下をあえて精査不要としたガイドラインの考えとも一致するものと考えられました。
一つ目は、サイズが5mm前後の腫瘤に対しての扱い方で、経過観察にはなるものの所見に対して施設からは診断名を記載せねばならず、この場合診断医によってバラバラになってしまうという検診施設での問題についてその取り扱いについてディスカッションしていきました。この様な病変の場合、様々な考え方が出され一つにまとめることは難しかったのですが、会場にいた多くの方達に共通していたのは、今回提示された小腫瘤は全て悪性を考えにくいと判定されたことでした。これは検診を行う上では非常に重要であり、5mm以下をあえて精査不要としたガイドラインの考えとも一致するものと考えられました。  三つ目はドプラの扱い方についてでした。どの様な病変に対してドプラを行えばよいのか?また、どの様な手法を用いればよいのか?普段知る機会の少ないドプラ法に対して少しでも解決できればとの思いで画像提示をして頂きました。ドプラ法の克服には諸先輩達のアドバイスも重要ですが各施設で使用している機器メーカーの方達にもアドバイス等協力してもらいながら解決していく必要があるとのコメントをフロアから頂きました。
三つ目はドプラの扱い方についてでした。どの様な病変に対してドプラを行えばよいのか?また、どの様な手法を用いればよいのか?普段知る機会の少ないドプラ法に対して少しでも解決できればとの思いで画像提示をして頂きました。ドプラ法の克服には諸先輩達のアドバイスも重要ですが各施設で使用している機器メーカーの方達にもアドバイス等協力してもらいながら解決していく必要があるとのコメントをフロアから頂きました。  この時点で既に時間となってしまい、症例提示は終了させて頂きました。
この時点で既に時間となってしまい、症例提示は終了させて頂きました。