

第21回北海道乳腺超音波研究会終了報告『学会発表のすすめ』 |
| 日 時 : 2018年2月24日(土) 14:00〜16:30 会 場 : ムトウホール |
|
プログラム

| 13:00〜 | 受 付 開 始 |
| 14:00〜14:05 | 開 会 の 辞 |
| 14:05〜 14:15〜 |
「抄録の読み方」に沿った抄録チェックの時間 各演者(5名)からの発表 |
| 15:30〜 | 休憩 |
| 15:45〜 | 全体質問時間 |
| 16:30 | 閉会の辞 |
演題を発表していただいた5名の演者(発表順)  ・小野寺 亜希さん (苫小牧市立病院 臨床検査科) ・小野寺 亜希さん (苫小牧市立病院 臨床検査科) 「乳癌との鑑別を要した乳腺アミロイドーシスの 1 例」 ・松下 麻衣子さん (勤医協中央病院 検査科) 「画像上悪性が疑われた乳腺血管腫の1例」 ・大杉 美幸さん (札幌乳腺外科クリニック) 「MMG上石灰化のみを示す乳癌のUS所見の特徴」 ・石本 博基さん (札幌厚生病院 放射線技術科) 「乳がん検診におけるUS同時併用・総合判定方式の検討」 ・佐藤 恵美さん (北海道大学病院 医療技術部放射線部門) 「造影超音波検査を用いた乳癌術前内分泌療法における早期治療効果予測の試み」 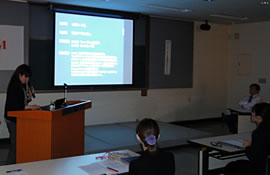  |
| 【参加者からの感想】 | |
| ・ | 抄録の読み方を学びました。抄録をしっかり読んでから演題の発表を聞くことで発表の内容をより深く理解することができ、疑問も必ずでてくるのだと学びました。 |
| ・ | 学会発表を積極的にしていくにはどうしたらよいかを一緒に考え、学会発表できない理由などを細かく聞くことで、各施設の問題点や解決策をあぶり出し、少しでも多くの方が進んで学会発表できるように話し合えたことがよかったと思います。 |
| ・ | 学会発表や講師を務めることで自分のモチベーションがあがるものなのだと実感しました。また、発表する材料については外に目を向けて今世の中が何を知りたいのかを考えることが大事ということ、それを知るためには積極的に学会や勉強会に参加すること、日々行っている業務の中でも常に疑問をもち追及していくことが大切なのだということを学びました。 |
| ・ | 「抄録の読み方」の資料がとてもよくできていて、読み方=書き方のお手本として今後に活かせる貴重な財産となりました。自分も何回か演題発表をする機会をいただいた中で、試行錯誤を繰り返し、指導してもらいながらやっと「こうすればいいんだ」という事が分かってきた気がします。 |
| ・ | 発表終了後のディスカッションでは「何故発表するに至らないか」について意見が出されていましたが、自分もなかなかテーマを見つけられずに悩んでいるほうだったので、とても参考になりました。日常の検査の中で浮かんできたわずかな疑問や発想を大切にし、今後も学会発表に取り組んでいきたいと思いました。 |
| ・ | 演題発表からは、乳腺アミロイドーシスや乳腺血管腫といった稀な疾患の症例を聞くことができ、頻度は少ないとはいえどもわずかな特徴をしっかりと理解し、腫瘤性病変の一つとして鑑別にあげられるようにしたいと思いました。 |
| ・ | DCISのような腫瘤を形成しないものも低エコー域や石灰化を探すといった基本的な考え方をあらためて学ぶことができた。低エコー域ととったものも、腫瘤なのではないか?と疑って様々な角度から描出し考える必要があり、経験が浅いからといった検者間の誤差にならないように注意したいと思った。 |
| ・ | 今回は、学会発表のすすめということもあり、演者とフロアの意見交換がなされており、発表に向けての大変さやその分のやりがい、業務に活かせる点なども聞くことができ、すぐにとはならないものの、自分が発表するときのための参考となるお話がたくさん聞けて、とても勉強になった。 |
| ・ | 今までこのようなテーマでの企画を目にしたことはなかったので、素晴らしい試みと思っていました。貴研究会での参加型の症例検討は、比較的発言しやすい雰囲気で、所見の読み方など大変勉強になると感じていますが、今回のようなテーマも、人材育成という意味で重要だと思いました。次回以降にも、今回のように全国学会で発表した内容をもう一度的な感じで、1,2題でも一般演題発表があってもよいのかな、と思いました。 |
| ・ | 乳腺に関する発表をまとめて聞くことができて良かったです。日常検査をしていると、貴重な経験・症例は少なく、なかなか発表を行う動機、きっかけがないように感じています。また、いざ発表するとなると確かにどのようにすすめていくか、自分一人ではわからないことも多く、先輩方を頼りにするしかないですが、このように発表までの過程も含めて講演するというのも、新しくておもしろいと感じました。 |
| ・ | 今後の希望としては造影に関して講演をして欲しいです。実際にやってみると、細かい手技について疑問が出てきたり、リンパ節の評価や乳管内進展の評価方法が難しく感じています。プローブより大きな腫瘤の評価はどこまでできるのかなど、造影でできること、限界がどこなのかなど知りたいです。限界があるならどのように医師に理解してもらうか等も知りたいです。 |
| ・ | 研究会に簡単でもよいので、Q&Aなどあると質問もしやすいし、同じ疑問を持つ人にも役立つのではないかと思います。 |
| ・ | 5演題の発表の後、発表者の方から発表の契機となった事柄や発表までの準備方法などを解説していただきました。このような内容のテーマで学習会が開かれることは今までなく、身近な先輩からの助言を受けて発表準備を行っていたので他の方たちも同じようなことで悩んでいることがわかった。 |
| ・ | 初めからきちんとした流れが出来ていなくていいので、普段の業務の中で疑問に思ったことを調べていくことで広がりがでて発表できる内容になるので疑問に思ったことをそのままにしない。目新しい内容の発表をしようとせず、既に発表されている内容が自施設ではどうか?という検討をする。いきなり学会ではハードルが高いので研究会などに気になる画像を持っていくなどから始めていく。色々なアドバイスを頂いた。 |
| ・ | 検診センターの方からは自分達が行った検査で指摘した所見が本当はどの様な結果だったのかがわからない。という意見が出た。精査する側は所見がきちんと書いていないのでどこが気になったのかわからないし、返事も書けない。当院ではどうなっているのか気になった。 |
| ・ | 3演題目の内容から、よくMMGで石灰化の集簇がありエコーの検査が出るが石灰化だけではなく低エコー部分があることが重要だと発表がありこれからの業務で役立てたい。学会発表に苦手意識があるが業務中に気になったことを調べていくことから少しずつ始めていくことが大切だと感じた。 |
トップページへ戻る
 2018年2月24日(土)に第21回北海道乳腺超音波研究会が開催されました。
2018年2月24日(土)に第21回北海道乳腺超音波研究会が開催されました。  る会員の方々が、各所属学会などで発表してきた「乳腺」にかかわる大変興味深い演題を研究会においてもう一度ご発表いただき、その発表内容を改めてじっくりと学ばせていただくという企画を考えました。
る会員の方々が、各所属学会などで発表してきた「乳腺」にかかわる大変興味深い演題を研究会においてもう一度ご発表いただき、その発表内容を改めてじっくりと学ばせていただくという企画を考えました。