 ようやく北海道にも春の気配が濃くなってきました。平成28年3月26日(土)の研究会は、JA札幌厚生病院にて開催されました。参加91名と、初めての会場であったにもかかわらず、多数の参加となりました。 ようやく北海道にも春の気配が濃くなってきました。平成28年3月26日(土)の研究会は、JA札幌厚生病院にて開催されました。参加91名と、初めての会場であったにもかかわらず、多数の参加となりました。
過去2回(第16.17回)の研究会では「超音波診断装置に学ぶ〜・・」と題して、 乳腺超音波画像の画質改善による診断能向上を目指して、東芝メディカルシステムズ社と日立アロカメディカル社による機器調整に関する技術およびアプリケーションの説明と、それらを実施に使用しているユーザーによって現状を報告いただきました。 乳腺超音波画像の画質改善による診断能向上を目指して、東芝メディカルシステムズ社と日立アロカメディカル社による機器調整に関する技術およびアプリケーションの説明と、それらを実施に使用しているユーザーによって現状を報告いただきました。
今回は、過去2回で報告して頂いた9名2社のアプリケーション担当者である東芝メディカル社の石田 歩さんと日立アロカ社の大野 千恵さんと共に、前回以降の画像の設定条件変更による変化についての報告を行い、その後全発表者と総合討論を行うというこれまでない形式で進行されました。この間の司会進行はいつもの通り白井代表が行いました。
 開始はまず、当会の世話人でもある勤医協札幌病院の高橋智子さんにこのような企画となった経緯について説明を頂きました。発端はさかのぼること2010年3月に開催された第6回北海道乳腺超音波研究会での症例検討において、症例の供覧時に装置ごとに画像の違いがある事に対して問題提起された事で、その後同年10月に札幌で行われたJABTS第25回学術集会では「超音波診断装置のPRESET による乳腺画像の変化についての検討」 として北海道乳腺超音波研究会の研究発表が行われました。この中で周波数・ゲイン・ダイナミックレンジ・フォーカスの設定はもちろんの事、当時からすでに高画質化機能の設定としてTHI空間コンパウンド 周波数コンパウンド、スペックルリダクションなどに関しても検討なされておりました。当時の考察では、この様な高画質化機能によって品質の高い画像は得られるが、はたして装置毎の性能を十分に引き出しているかについては疑問が残るとされていました。以上のような過程説明の後、8名のスピーカーからの報告が行われました. 開始はまず、当会の世話人でもある勤医協札幌病院の高橋智子さんにこのような企画となった経緯について説明を頂きました。発端はさかのぼること2010年3月に開催された第6回北海道乳腺超音波研究会での症例検討において、症例の供覧時に装置ごとに画像の違いがある事に対して問題提起された事で、その後同年10月に札幌で行われたJABTS第25回学術集会では「超音波診断装置のPRESET による乳腺画像の変化についての検討」 として北海道乳腺超音波研究会の研究発表が行われました。この中で周波数・ゲイン・ダイナミックレンジ・フォーカスの設定はもちろんの事、当時からすでに高画質化機能の設定としてTHI空間コンパウンド 周波数コンパウンド、スペックルリダクションなどに関しても検討なされておりました。当時の考察では、この様な高画質化機能によって品質の高い画像は得られるが、はたして装置毎の性能を十分に引き出しているかについては疑問が残るとされていました。以上のような過程説明の後、8名のスピーカーからの報告が行われました.
 まず東芝メディカルユーザーの3名にお話しいただきましたが、トップバッターはJCHO北海道病院 相馬 真弓さんで、『画像表示の大きさによって画像の印象が異なること、また周波数の選択によって内部エコーに差があることを理解して考えてゆきたい』とのことでした。 まず東芝メディカルユーザーの3名にお話しいただきましたが、トップバッターはJCHO北海道病院 相馬 真弓さんで、『画像表示の大きさによって画像の印象が異なること、また周波数の選択によって内部エコーに差があることを理解して考えてゆきたい』とのことでした。
次に(医)新産健会スマイル健康クリニックの日下部 恵さんは前回の報告時にゲイン調整に関してアドバイスを受け、 『アプリ担当者とポストプロセスやガンマカーブの再調整を行った結果、情報量はあがったものの、全体的に視認性が落ちてしまった事より、検討前の設定条件で検査を行っている。』とのことでした。但し、ここでの問題となったのが装置のモニターであり、その性能の為にこの様な逆転現象が生じたのではないかと考えられました。 『アプリ担当者とポストプロセスやガンマカーブの再調整を行った結果、情報量はあがったものの、全体的に視認性が落ちてしまった事より、検討前の設定条件で検査を行っている。』とのことでした。但し、ここでの問題となったのが装置のモニターであり、その性能の為にこの様な逆転現象が生じたのではないかと考えられました。
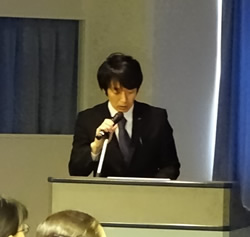 3人目は網走厚生病院の岩間 寛さんで、前回の指摘内容とその後の検討を詳細に報告頂きました。『前回指摘は、プリセットの周波数が高かった為に深部減衰が目立っていたが、開始周波数を10MHzに設定した事で、深い位置の描出がよくなった。コンパウンドとアプリピュアは基本はなしで開始しているが、場合によって軽度に効かせる事で利益があると思われる。ハーモニックはフレームレートに 3人目は網走厚生病院の岩間 寛さんで、前回の指摘内容とその後の検討を詳細に報告頂きました。『前回指摘は、プリセットの周波数が高かった為に深部減衰が目立っていたが、開始周波数を10MHzに設定した事で、深い位置の描出がよくなった。コンパウンドとアプリピュアは基本はなしで開始しているが、場合によって軽度に効かせる事で利益があると思われる。ハーモニックはフレームレートに 影響があるが、かけたほうが全体のコントラストはいいように感じる。』との報告でした。 影響があるが、かけたほうが全体のコントラストはいいように感じる。』との報告でした。
10分間の休憩ののち、日立アロカユーザーの4人の発表で、最初はメディカルプラザ札幌健診クリニックの菅原智子さんの報告で、『これまで高周波のみ行っていた検査を開始時には低周波で行い、受診者の乳腺によって周波数を変える、ということで特に深部の描出が改善されたため、全体的な画質の向上から業務の効率化にも役立っている。普段トラペソイド画像を使用して検査しているが深い位置の分解能が下がると思う。』という発表でした。 トラペソイド画像については、白井代表からは『画質をやや犠牲にしてもリアルタイムに周囲情報も含みながら走査できる利点がある。ただ通常のリニア画像との画質差については理解しておくべき』との追加発言がありました。 トラペソイド画像については、白井代表からは『画質をやや犠牲にしてもリアルタイムに周囲情報も含みながら走査できる利点がある。ただ通常のリニア画像との画質差については理解しておくべき』との追加発言がありました。
続いて札幌厚生病院の北口一也さん。施設内の日常検査においてプリセットの「デフォルト」と「ファンダメンタル」の2つを使い分けており、前回の報告では形態の境界はデフォルトが、内部構造はファンダメンタルが良いという結果でした。今回はそれぞれのプリセットを再び修正した上で検討した結果、以前より視認性が改善されたため、複数のスタッフが使用しても見落としのない画像となり、通常はデフォルトで検査を開始し、精査が必要な場合はこちらも画質の改善したファンダメンタルを追加して行うという目的別プリセット選択ができたという報告でした。
 次に製鉄記念室蘭病院の鈴木綾子さんは、前回の内容について研究会に参加できなかった施設のスタッフと共に画像設定のための検討会を開き、画像改善の取り組み行った。『実際の検討内容による変更は、リアルタイム性をよくするためフォーカスの数を2点から1点に、また音速補正を1440 m/sに変更した。加えてAIPをオン,オフすることによって以前より画像の改善が見られ、実際の検査成績にも寄与することが期待された。』という発表でした。代表から画質向上の原因としてフォーカスの数だけでここまで変化するのかという質問に対し、アプリ担当者からは、今回の変更でフレームレートも上がり、走査線密度の向上もあったためではという回答を頂きました。 次に製鉄記念室蘭病院の鈴木綾子さんは、前回の内容について研究会に参加できなかった施設のスタッフと共に画像設定のための検討会を開き、画像改善の取り組み行った。『実際の検討内容による変更は、リアルタイム性をよくするためフォーカスの数を2点から1点に、また音速補正を1440 m/sに変更した。加えてAIPをオン,オフすることによって以前より画像の改善が見られ、実際の検査成績にも寄与することが期待された。』という発表でした。代表から画質向上の原因としてフォーカスの数だけでここまで変化するのかという質問に対し、アプリ担当者からは、今回の変更でフレームレートも上がり、走査線密度の向上もあったためではという回答を頂きました。
 東旭川病院の鬼柳 かおりさんは、前回と比較してプリセットを変えたのはAIPのみという話でした。『自分としては今までの画像にも満足はしていたが、AIPを入れる事でより分解能の改善が見られ、診断よい影響が期待できる、という報告でした。アプリの方からはAIPは画像のつながりが良くなり、尚且つフレームレートに影響しないとの事でした。 東旭川病院の鬼柳 かおりさんは、前回と比較してプリセットを変えたのはAIPのみという話でした。『自分としては今までの画像にも満足はしていたが、AIPを入れる事でより分解能の改善が見られ、診断よい影響が期待できる、という報告でした。アプリの方からはAIPは画像のつながりが良くなり、尚且つフレームレートに影響しないとの事でした。
 最後は帯広厚生病院の中屋 俊介さんで、前回の反省から画像の改善のために大きく4点の改定を示されました。改定した4点の内、高機能部分をな くしたり程度を減らしたりした点や、そのほかにダイナミックレンジを若干上げたとのことより、画像がシャープになり、追従性も改善した。画像の実際の診断には少し慣れが必要な部分もあったものの、大きい腫瘤の深部方向の分解能が改善されたとの報告でした。 最後は帯広厚生病院の中屋 俊介さんで、前回の反省から画像の改善のために大きく4点の改定を示されました。改定した4点の内、高機能部分をな くしたり程度を減らしたりした点や、そのほかにダイナミックレンジを若干上げたとのことより、画像がシャープになり、追従性も改善した。画像の実際の診断には少し慣れが必要な部分もあったものの、大きい腫瘤の深部方向の分解能が改善されたとの報告でした。
この後に総合討論が行われました。
代表からスピーカーの皆さんへ今回の企画に参加しての印象をお話くださいという問いに対し以下のような意見がありました。
- 教科書で勉強した画像と実際の装置で行った場合に画像画質のギャップがある事に気づき、このような検討の必要性が認識出来た。今回のような試みがその手がかりになると思う。
- 日常検査で適正な検査時間内で行うこと、あるいは教育することの解決法としては症例を多く見ることも大切だが、正常をしっかり見ることや、1つの症例を最後まで突き詰めて追跡することも大きな学びになる。
- 現在使用している機械の性能の限界を今回の検討に参加することで知ることができ、その上で検診施設として精査が必要な対象はなんとかピックアップするという役割を果たせているという確信が持てた。
- 検討にあたり多くの画像処理がありすぎて、
 何を選択すべきかが難しかった。そのような中周波数の変更とそれに付随することのみに形となったが、それでも検査時には十分な画像が得られることがわかった。 何を選択すべきかが難しかった。そのような中周波数の変更とそれに付随することのみに形となったが、それでも検査時には十分な画像が得られることがわかった。
- 今回の検討によって検討した装置の画質の向上は図れた実感はある。ただ違うメーカーの装置に関してその調整をどのようにしていったら良いのか悩んでいるとの事に対して、代表からはたとえばフレームレートや深部感度などは落とさないなどといった重要と考える基本事項を守って後は、それぞれの装置の良い点を生かして行く調整がいいのではという追加発言があった。
- これまで超音波検査担当が臓器別に分かれていたスタッフが、画質調整という同じスタンスで装置に携わり、お互いのコミュニケーション向上とスキルアップにつながった。
以上内容は多岐にわたっていましたが、経験の多少にかかわらず熱心な発表者の皆さんのおかげで大変前向きな内容となりました。 |


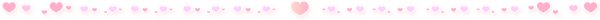
 ようやく北海道にも春の気配が濃くなってきました。平成28年3月26日(土)の研究会は、JA札幌厚生病院にて開催されました。参加91名と、初めての会場であったにもかかわらず、多数の参加となりました。
ようやく北海道にも春の気配が濃くなってきました。平成28年3月26日(土)の研究会は、JA札幌厚生病院にて開催されました。参加91名と、初めての会場であったにもかかわらず、多数の参加となりました。  乳腺超音波画像の画質改善による診断能向上を目指して、東芝メディカルシステムズ社と日立アロカメディカル社による機器調整に関する技術およびアプリケーションの説明と、それらを実施に使用しているユーザーによって現状を報告いただきました。
乳腺超音波画像の画質改善による診断能向上を目指して、東芝メディカルシステムズ社と日立アロカメディカル社による機器調整に関する技術およびアプリケーションの説明と、それらを実施に使用しているユーザーによって現状を報告いただきました。  開始はまず、当会の世話人でもある勤医協札幌病院の高橋智子さんにこのような企画となった経緯について説明を頂きました。発端はさかのぼること2010年3月に開催された第6回北海道乳腺超音波研究会での症例検討において、症例の供覧時に装置ごとに画像の違いがある事に対して問題提起された事で、その後同年10月に札幌で行われたJABTS第25回
開始はまず、当会の世話人でもある勤医協札幌病院の高橋智子さんにこのような企画となった経緯について説明を頂きました。発端はさかのぼること2010年3月に開催された第6回北海道乳腺超音波研究会での症例検討において、症例の供覧時に装置ごとに画像の違いがある事に対して問題提起された事で、その後同年10月に札幌で行われたJABTS第25回 まず東芝メディカルユーザーの3名にお話しいただきましたが、トップバッターはJCHO北海道病院 相馬 真弓さんで、『画像表示の大きさによって画像の印象が異なること、また周波数の選択によって内部エコーに差があることを理解して考えてゆきたい』とのことでした。
まず東芝メディカルユーザーの3名にお話しいただきましたが、トップバッターはJCHO北海道病院 相馬 真弓さんで、『画像表示の大きさによって画像の印象が異なること、また周波数の選択によって内部エコーに差があることを理解して考えてゆきたい』とのことでした。  『アプリ担当者とポストプロセスやガンマカーブの再調整を行った結果、情報量はあがったものの、全体的に視認性が落ちてしまった事より、検討前の設定条件で検査を行っている。』とのことでした。但し、ここでの問題となったのが装置のモニターであり、その性能の為にこの様な逆転現象が生じたのではないかと考えられました。
『アプリ担当者とポストプロセスやガンマカーブの再調整を行った結果、情報量はあがったものの、全体的に視認性が落ちてしまった事より、検討前の設定条件で検査を行っている。』とのことでした。但し、ここでの問題となったのが装置のモニターであり、その性能の為にこの様な逆転現象が生じたのではないかと考えられました。 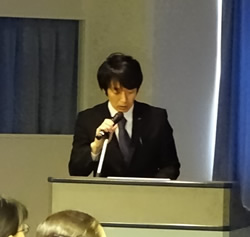 3人目は網走厚生病院の岩間 寛さんで、前回の指摘内容とその後の検討を詳細に報告頂きました。『前回指摘は、プリセットの周波数が高かった為に深部減衰が目立っていたが、開始周波数を10MHzに設定した事で、深い位置の描出がよくなった。コンパウンドとアプリピュアは基本はなしで開始しているが、場合によって軽度に効かせる事で利益があると思われる。ハーモニックはフレームレートに
3人目は網走厚生病院の岩間 寛さんで、前回の指摘内容とその後の検討を詳細に報告頂きました。『前回指摘は、プリセットの周波数が高かった為に深部減衰が目立っていたが、開始周波数を10MHzに設定した事で、深い位置の描出がよくなった。コンパウンドとアプリピュアは基本はなしで開始しているが、場合によって軽度に効かせる事で利益があると思われる。ハーモニックはフレームレートに 影響があるが、かけたほうが全体のコントラストはいいように感じる。』との報告でした。
影響があるが、かけたほうが全体のコントラストはいいように感じる。』との報告でした。  トラペソイド画像については、白井代表からは『画質をやや犠牲にしてもリアルタイムに周囲情報も含みながら走査できる利点がある。ただ通常のリニア画像との画質差については理解しておくべき』との追加発言がありました。
トラペソイド画像については、白井代表からは『画質をやや犠牲にしてもリアルタイムに周囲情報も含みながら走査できる利点がある。ただ通常のリニア画像との画質差については理解しておくべき』との追加発言がありました。  次に製鉄記念室蘭病院の鈴木綾子さんは、前回の内容について研究会に参加できなかった施設のスタッフと共に画像設定のための検討会を開き、画像改善の取り組み行った。『実際の検討内容による変更は、リアルタイム性をよくするためフォーカスの数を2点から1点に、また音速補正を1440 m/sに変更した。加えてAIPをオン,オフすることによって以前より画像の改善が見られ、実際の検査成績にも寄与することが期待された。』という発表でした。代表から画質向上の原因としてフォーカスの数だけでここまで変化するのかという質問に対し、アプリ担当者からは、今回の変更でフレームレートも上がり、走査線密度の向上もあったためではという回答を頂きました。
次に製鉄記念室蘭病院の鈴木綾子さんは、前回の内容について研究会に参加できなかった施設のスタッフと共に画像設定のための検討会を開き、画像改善の取り組み行った。『実際の検討内容による変更は、リアルタイム性をよくするためフォーカスの数を2点から1点に、また音速補正を1440 m/sに変更した。加えてAIPをオン,オフすることによって以前より画像の改善が見られ、実際の検査成績にも寄与することが期待された。』という発表でした。代表から画質向上の原因としてフォーカスの数だけでここまで変化するのかという質問に対し、アプリ担当者からは、今回の変更でフレームレートも上がり、走査線密度の向上もあったためではという回答を頂きました。  東旭川病院の鬼柳 かおりさんは、前回と比較してプリセットを変えたのはAIPのみという話でした。『自分としては今までの画像にも満足はしていたが、AIPを入れる事でより分解能の改善が見られ、診断よい影響が期待できる、という報告でした。アプリの方からはAIPは画像のつながりが良くなり、尚且つフレームレートに影響しないとの事でした。
東旭川病院の鬼柳 かおりさんは、前回と比較してプリセットを変えたのはAIPのみという話でした。『自分としては今までの画像にも満足はしていたが、AIPを入れる事でより分解能の改善が見られ、診断よい影響が期待できる、という報告でした。アプリの方からはAIPは画像のつながりが良くなり、尚且つフレームレートに影響しないとの事でした。  最後は帯広厚生病院の中屋 俊介さんで、前回の反省から画像の改善のために大きく4点の改定を示されました。改定した4点の内、高機能部分をな くしたり程度を減らしたりした点や、そのほかにダイナミックレンジを若干上げたとのことより、画像がシャープになり、追従性も改善した。画像の実際の診断には少し慣れが必要な部分もあったものの、大きい腫瘤の深部方向の分解能が改善されたとの報告でした。
最後は帯広厚生病院の中屋 俊介さんで、前回の反省から画像の改善のために大きく4点の改定を示されました。改定した4点の内、高機能部分をな くしたり程度を減らしたりした点や、そのほかにダイナミックレンジを若干上げたとのことより、画像がシャープになり、追従性も改善した。画像の実際の診断には少し慣れが必要な部分もあったものの、大きい腫瘤の深部方向の分解能が改善されたとの報告でした。  何を選択すべきかが難しかった。そのような中周波数の変更とそれに付随することのみに形となったが、それでも検査時には十分な画像が得られることがわかった。
何を選択すべきかが難しかった。そのような中周波数の変更とそれに付随することのみに形となったが、それでも検査時には十分な画像が得られることがわかった。